VOICE~岐大医学部から~
泌尿器科学分野からのメッセージ
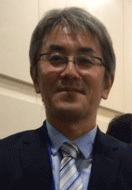
医学系研究科 病態制御学講座
泌尿器科学分野
教授 古家 琢也 先生
『VOICE-岐大医学部から-』第94回は、平成30年8月に就任されました、医学系研究科 病態制御学講座 泌尿器科学分野 教授 古家 琢也先生にお話を伺いました。
医師になられたきっかけは?
私は、幼少期とても体が弱く、月の半分幼稚園を休むような子供でした。その時のかかりつけの先生(開業されていた外科の先生でしたが)の対応に、子供ながらに感銘を覚え、5歳の時にはすでに医師を志すようになっていました。その後、目標は一度もぶれることはありませんでした。大学受験でも、自分は当然医師になるものだと思っていましたので(今思うと、随分怖いもの知らずであったと思いますが)、私立大学などは一切受験せず、国立大学医学部のみを受験しました。運よく弘前大学に入ることができ、現在に至っています。
どのような研究を行っていますか?
臨床で直面した問題を、どうしたら解決できるのか、どんな手法を取るべきか、といったことが私の研究を発想する上での起点となっています。同じ治療をしてもなぜ効果に差が出るのか、なぜ予後不良な患者がいるのか、という疑問を解決するための糸口として、コリンエステラーゼやグレリンという物質に着目して研究を行っています。また、不要な検査を回避するためのマーカーの開発、癌の浸潤過程に関する研究も行ってきました。一方臨床では、予後に改善を目的とした、術前化学療法とロボット手術を組み合わせた集学的治療の開発、自排尿可能な新膀胱の術式の確立とその排尿機序の解明といったことを行ってきました。新膀胱に関しては、今後ロボットを用いて、より簡便で誰でも作成可能な術式の確立に取り組んでいきたいと考えています。
教室をどのようにもり立てて行きたいですか?
私の医療に対するスタンスは、すべては患者のために、ということです。一人の患者に真摯に向き合い、最適な治療を常に模索していくような医師を育てたいと思っています。そのため、カンファレンスはとても重要だと思っています。その中で、自分の思ったことを気軽に発言できるような、明るい教室を作っていければと考えています。若い先生たちには、より積極的に手術を担当してもらうことで、仕事に対する誇りとやりがいを実感してほしいと考えていますし、上級医に対しては、後輩に対して様々な指導(手術のみならず,論文指導や患者に対する対応など)を行うことで、技術のみならず、人としてより成長していただきたいと思っています。そのための土台作りをし、医局の先生方の成長の手助けをしていきたいと考えています。
医師を目指す学生へのメッセージ
医師という職業は、私自身はとても素晴らしい仕事の一つだと考えています。確かにやりがいのある仕事ですが、一方で精神的・肉体的にもタフであることが要求されます。それは、何日も寝ないで仕事をするといったことを指すのではありません。医師も人間ですから、心にも波があります。疲れてくれば、イライラすることもあります。人は未熟なもので、自分の精神状態が不安定になると周りに当たることもあります。確かに方針の決定や実際の治療は医師の責任で行いますが、独りでやれることには限界があります。適切な医療を行うためには、周りのスタッフの協力が必要不可欠です。ですから、自分の心が不安定になった時こそ、心をフラットに保つことが肝要です。その姿を見せることで、患者やスタッフの安心感につながり、信頼される医師へと成長していくのだと思っています。その習得に、近道はありません。日々の積み重ねがとても大事です。学生時代には、勉強も必要ですが、是非多くの先輩・後輩と触れ合ってください。部活も、是非一生懸命取り組んでください。多くの喜びや挫折を経験してください。その経験のすべてが、自分の人間力を成長させ、それが立派な医師への一歩となるはずです。皆さんの将来に、期待します。
略歴
| 1994年 | 弘前大学医学部 卒業 |
|---|---|
| 1998年 | 弘前大学大学院医学研究科 卒業 |
| 1999年 | 弘前大学医学部附属病院 医員 |
| 弘前大学医学部 助手 | |
| 2002年 | 弘前大学医学部附属病院 講師 |
| 2004年 | 弘前大学泌尿器科 病棟医長兼務 |
| 2005年 | 弘前大学泌尿器科 外来医長兼務 |
| 2008年 | 弘前大学泌尿器科 病棟医長兼務 |
| 2012年 | 弘前大学 泌尿器科 総医長兼務 |
| 弘前大学医学研究科 准教授 | |
| 2013年 | 弘前大学医学部附属病院部署リスクマネージャー |
| 2016年 | 弘前大学医学部附属病院 臨床教授 |
| 2018年8月 | 現職 |
