VOICE~岐大医学部から~
退職教授からのメッセージ

医学系研究科 分子・構造学講座
病態情報解析医学分野
教授 清島 満 先生
『VOICE-岐大医学部から-』第89回は、平成30年3月をもって退職される、医学系研究科 分子・構造学講座 病態情報解析医学分野 教授 清島 満 先生にお話を伺いました。
教員生活を振り返って
教員ポストに初めて就いたのは第一内科から当時の中央検査部に助手として移った時で、それから講師を経て平成9年6月に教授に就任しました。研究テーマはアポ蛋白代謝と動脈硬化で随分たくさんのマウスやラットを使いましたが、研究そのものは自分なりに満足のいく成果が得られたと思っています。検査部と輸血部の管理運営については検査技師職員の皆さんが有能だったので、大過なく勤めあげることができました。平成16年の病院移転の時はさすがに緊張しましたが、これも大きなトラブルはありませんでした。また現在はISO15189取得のために検査部および輸血部の全職員が頑張っており、年内に無事取得できるものと思います。診療では以前は高脂血症外来を担当していましたが、病院移転後は総合内科で初診・再診を担当させていただきました。大学病院の総合内科はいくつかの病院を経て受診されるケースが多くて診断が難しく、かつ精神的な問題をかかえている患者さんも多いという印象があり、対応に苦慮することもありました。教育についてはテュトーリアルコースの分担講義のほか、臨床実習では検査の有用性を講義し、経済性も含めた効率性を強調しました。
平成24年4月からの4年間、医学系研究科長・医学部長を務めましたが、様々な問題が山積して当初はかなり戸惑いました。最初の仕事は文科省からの通達で、「ミッションの再定義」を纏めよというものでした。事務の方にも資料集めなどを手伝ってもらいながらの大変な作業でした。そして何回か文科省とやり取りした後、完成したものはA4版1枚におさまる程度のもので、たったこれだけかと虚脱感に陥りました。その一方、当時の教務厚生委員会と医学教育開発研究センターの頑張りのおかげで昨年12月に医学教育分野別評価が日本医学教育評価機構(JACME)より正式に認定されたことは大変喜ばしいことでした。
34年間の教員生活は自分としては充実したものであったと感じており、ご支援頂いた周囲の皆さまに心から感謝を申し上げます。
次世代へのメッセージ
医学の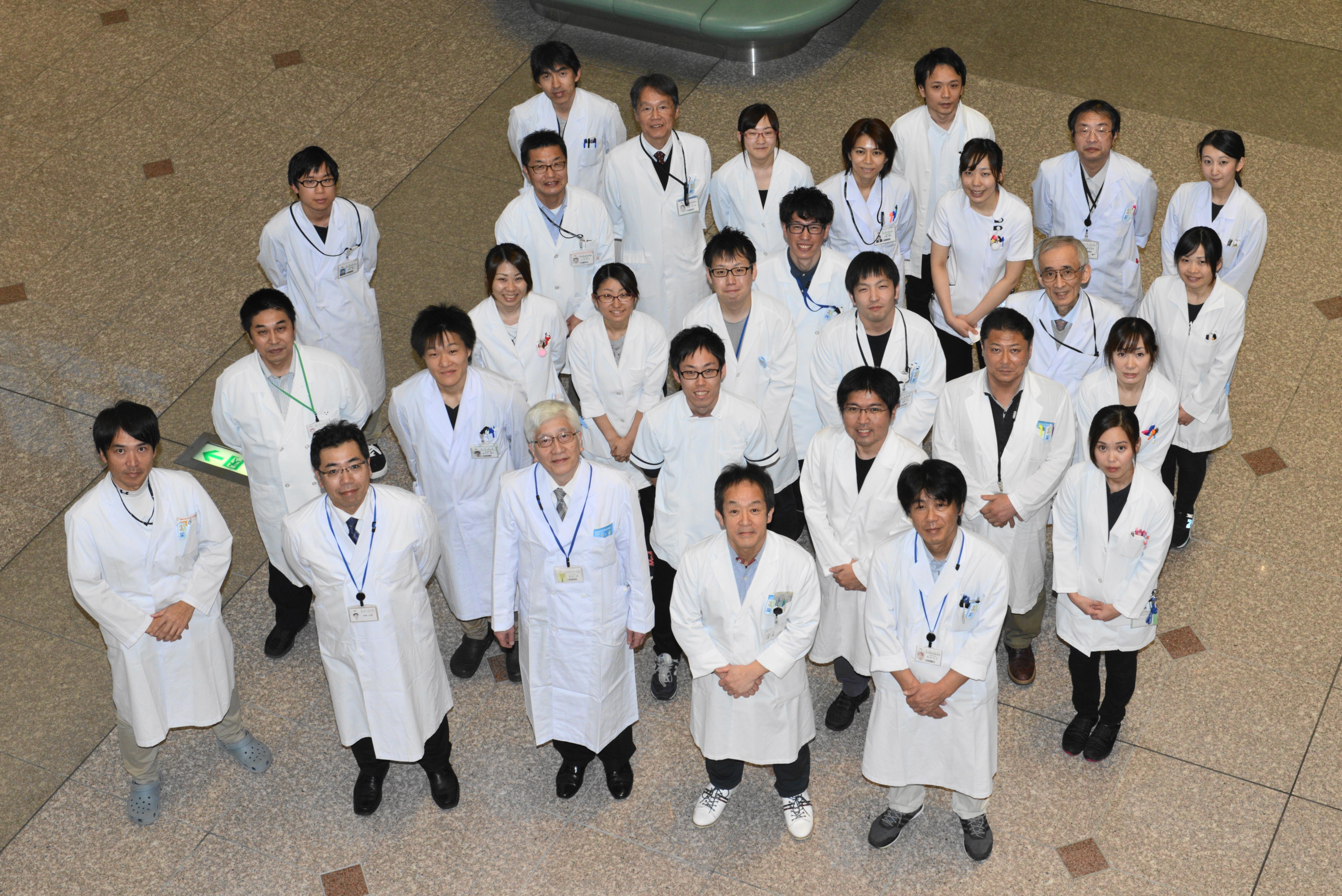
略歴
| 1952年生まれ、専門は臨床検査医学 | |
|---|---|
| 1978年 | 岐阜大学医学部 卒業 |
| 岐阜大学医学部附属病院第一内科 入局 | |
| 1985年 | 岐阜大学医学部附属病院中央検査部 助手 |
| 1988年 | 米国コロンビア大学医学部内科留学(2年間) |
| 1994年 | 岐阜大学医学部附属病院中央検査部 講師 |
| 1997年 | 岐阜大学医学部臨床検査医学 教授 |
| 岐阜大学医学部附属病院検査部 部長 | |
| 1999年 | 岐阜大学医学部附属病院輸血部 部長 |
| 2004年 | 岐阜大学大学院医学系研究科病態情報解析医学 教授 (組織改組による変更) |
| 2012年 | 岐阜大学大学院医学系研究科長・医学部長(4年間) |
| 2018年3月 | 退職 |
学会役員
| 日本臨床検査医学会(名誉会員、専門医) | |
|---|---|
| 日本臨床自動化学会(功労会員) | |
| 日本臨床化学会(評議員) | |
| 日本動脈硬化学会(専門医、指導医、評議員) | |
| 日本内科学会(認定医、評議員) | |
| 日本消化器病学会(専門医) | |
| 日本肝臓学会(専門医) |
