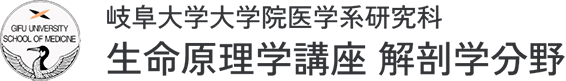教授挨拶

解剖学分野教授
江角 重行
岐阜大学大学院医学系研究科・医学部生命原理学講座解剖学分野(以下、解剖学分野)は、1950(昭和25)年4月に開設された旧制岐阜県立医科大学の解剖学第一講座に始まります。歴代の教授は、原淳教授(1950~1960年)、瀬戸口孝夫教授(1960~1970年)、磯野日出夫教授(1970~1993年)、正村静子教授(1993~2007年)、千田隆夫教授(2011~2025年)、江角重行(2025~ )と受け継がれてきました。75年の歴史の中で、研究室の名称は、解剖学第一講座、生体構造学講座、解剖学分野と変わりました。
医学部医学科の教育における"解剖学"の占める時間数は、常に基礎医学で最多でした。従来からの慣例を踏襲し、現在も解剖学分野が肉眼(マクロ)解剖学・発生学各論を担当し、高次神経形態学分野が顕微(ミクロ)解剖学・神経解剖学・発生学総論を担当しています。
人体の構造と機能は不可分であり、生理機能と病的過程のいずれにおいても、構造と機能の両者を知り、総合的に捉えることで初めて、医学を修めることが可能となります。解剖実習を通じて、緻密な人体の構造を体系的に理解し、リアルな感覚として身につけ、献体の方が"最初の患者さん"だという倫理感、教科書とは違う個人差があるという事実を学んでもらいたいと思っています。
最近加わった重要なミッションとして、岐阜大学医学部におけるカダヴァー・サージカル・トレーニング(CST)の支援があります。岐阜大学医学部に献体されたご遺体を管理する当分野でなければできない業務ですが、この目的のために、3年前より寄附講座・臨床解剖開発学講座(寄付者:岐阜県厚生農業協同組合連合会)が併設されました。詳細は岐阜大学医学部カダヴァー・サージカル・トレーニングセンターのウェブサイトをご覧ください。
私達は、献体していただいた方・登録していただいた方の崇高な志には心より感謝し、尊いご意志を実感しながら、業務行っております。スタッフ(献体業務に携わる教員・技術職員・事務職員)が一丸になって、綿密に連携をとり、ご遺体の適切な管理に努め、医学の発展と進歩のために尽力しています。
解剖学分野の現在の研究は、教員それぞれの学問的興味と研究歴を尊重して行っていますが、解剖学の伝統的な研究方法である形態学に加えて、細胞生物学、分子生物学、生化学等を積極的に取り入れています。詳細は「研究概要」をご覧ください。研究テーマによって教員が所属する学会は異なりますが、皆共通して入会しているのは、教育遂行上必須の日本解剖学会と分子レベルの形態学を標榜する日本臨床分子形態学会です。
解剖学は、かたちを見てはたらきをひも解く古くて新しい学問です。私たちは、これまでの解剖学研究を踏襲しつつも、分子生物学や細胞生物学的手法を取り入れ、基礎と臨床の架け橋となる研究に積極的に挑戦したいと思っています。人体の構造・組織・細胞・神経のかたちや、脳の発生・発達に興味がある学生は、気軽に研究室を訪ねて下さい。
江角重行(えすみしげゆき)
【略歴】
1993.3 島根県立安来高等学校 卒業
1998.3 広島大学理学部生物科学科 卒業
2000.3 広島大学大学院理学研究科 遺伝子科学専攻 修了
2005.3 大阪大学大学院理学研究科 生物科学専攻 修了(理学博士)
2005.4 熊本大学大学院医学薬学研究部 脳回路構造学分野 助手
2007.4 熊本大学大学院医学薬学研究部 脳回路構造学分野 助教
2009.8〜2011.7 Children's National Hospital (米国・ワシントンDC)
2017.7 熊本大学大学院生命科学研究部 脳回路構造学分野 講師
2020.4 熊本大学大学院生命科学研究部 形態構築学講座 講師
2025.4〜 岐阜大学大学院医学系研究科 生命原理学講座 解剖学分野 教授
【専門分野】神経解剖学、肉眼解剖学、神経発生・発達、シングルセル解剖学
【所属学会】日本解剖学会、日本神経科学学会、北米神経科学会、日本発生学会、神経発生討論会、日本臨床分子形態学会、日本組織細胞化学会