研修医手記
掲示分の内容に関する問い合わせは、掲示者本人に直接連絡してください。
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 研修医1年目
小木曽 太知 (part42)
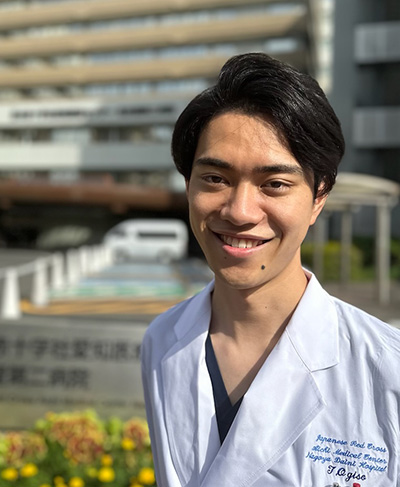
早く医師として働きたい。そう思いながら過ごしていた学生生活から一転して、日々の業務に忙殺されながらあっという間に研修医の1/4も過ぎてしまいました。正直、この6ヶ月で何ができるようになったのか、頼もしい先輩方に近づけているか、本当に自分は「医師」と名乗っていいのか、不安に苛まれる日々です。今回この研修医手記に投稿する機会をいただき、これまでの生活を振り返って日々感じたことを色々と書いていこうと思います。拙文で恐縮ですが、何卒お付き合いいただけると幸いです。
■できないことの多さに困惑する日々
学生時代はそれになりに勉強し、それなりに実習も頑張り、国家試験もクリアし、ある程度知識はあるものだと思っていましたが、現実の臨床はあまりにも乖離していました。単純に治療方法だけでなく、輸液、食事、栄養、リハビリ、社会的支援、他科やかかりつけとの連携など、多くのことを考えねばならず、国試は臨床における大前提に過ぎないことを痛感しました。治療法ひとつにしても、投与量、期間、方法、禁忌項目、病院での採用や保険収載など、知らないことだらけであり、それらを巧みに使いこなす先生方には驚愕しました。
知識面だけでなく、技術面でも課題だらけでした。研修生活の初日、病棟看護師さんから頼まれた末梢静脈路確保を今でも鮮明に覚えています。勉強したはずなのに、同期で練習したはずなのに、1人で実際の患者さんに行う恐怖は計り知れないものでした。手も声も震え、自分以上に患者さんを不安にさせてしまい、「もう先生はクビ、もっと上手い人呼んで」といわれて2年目の先生に泣きついてお願いしました。それからも毎日のように病棟の末梢静脈路確保に呼ばれ、自分なんかより慣れた上級医にやってもらう方が患者さんにとっていいのにと思う日々でした。しかしながら研修医の私に機会をいただいている以上はできる限りのことをしなくてはなりません。事前準備を徹底し、失敗したら原因を考えて次の患者さんに生きるようにしなくてはならないという責務を感じました。血管の探し方、エコー下での穿刺技術、ビニールに入れた温水で温めて血管拡張させる方法、他の人に手伝ってもらって駆血を効率的に行うことで穿刺部の血管を拡張させる方法。たかが末梢静脈路確保かもしれませんが、様々なことを教えていただいたり、勉強したりしました。1ヶ月後に再度同じ患者さんへの末梢静脈路確保を頼まれ、「先生、ちょっとは上手くなったじゃん」と言われた時にはこれほどなく嬉しかったです。末梢静脈路確保に限らず、胸腔穿刺、CV挿入、皮膚縫合、腰椎穿刺など、さまざまな手技の機会に恵まれていますが、こうした手技による侵襲や、合併症による患者さんへの不利益は、学生の頃には実感がなく、自分が臨床に出てはじめて痛感しました。
■責任感から生まれる意欲
私たちの病院での救急外来は研修医の裁量権が大きく、上級医にコンサルトせずに研修医だけで帰すことが多いです。自分が取った問診が違ったら、自分が取った身体所見やバイタルが違ったら、検査所見の解釈が違ったら。常に不安が付き纏うなか、次から次へと来る患者さんを診ていきます。自分が画像を読み落としたら、誰にも読まれることなくただ見逃される。そんな危機感から必死に食らいついて画像を見るようになり、勉強をするようになりました。しかしながら、はじめは異常が何か、異常があるかどうかさえもわからない状態でした。呼吸音の異常はあるけど、coarse crackleなのかrhonchiなのか。紅斑なのか膨疹なのか。この画像所見は出血か石灰化か。そもそもこれは病的意義のない正常変異なのかどうか。「すべては症状があると思って所見を取らないと見逃す。」異常と思う所見を拾い上げて1つ1つ勉強したり上級医の先生に相談したりする日々です。実際に所見を見逃して、翌日の一般外来で指摘されて注意を受けることもありました。「医者が無知であるのは研修医でも関係なく罪である。」そう言われて、医師という仕事に恐怖を強く感じました。
自分の能力不足が患者の死に直結すると実感した強烈な経験もしました。重症の救急車を診始めた頃、血便を主訴に運ばれた患者さんが自分の目の前で大量出血をし、みるみる間に顔面蒼白、ショックバイタルになっていたことを目の当たりにしました。その時に自分は適切な対処法が咄嗟に出ずにパニックになり、先生方に助けを呼ぶこともさえできませんでした。「目の前で患者が死ぬ。」この感覚は今までにない激烈なものでした。幸いにも看護師さんが上級医の先生方を呼んでくださり事無きを得ましたが、自分の圧倒的な無力感を痛感するとともに、「学ばねばならぬ」という強い感情を生みました。知識は「知る」から「使える」まで昇華させなければならないことを、実際に患者さんに接して、緊急を迫られて、初めて実感しました。教科書の知識を実践的にどうしていくのか、主体的になって考えながら勉強を進めていく重要さに気がつき、このモチベーションは学生の時には決して得られたものではなく、そして一生涯医師生活で大事にしていかなくてはならないと気が引き締まる毎日です。
その一方で、さまざまな主訴や重症度で患者さんは救急外来に来るため、全員がクリアカットに診断がついて治療できるわけではないです。検査で原因がわからず、はっきり診断がつかないと自分も不安になり、深追いしたくなったり、急がないのに上級医に相談したりしてしまいます。救急外来は緊急で処置治療が必要な患者さんに対して医療を提供する場所であり、診断をつける場所ではない、と常日頃言われている言葉を痛感します。「大丈夫というのも医師の仕事。」しっかりと裏打ちされた「大丈夫」を言えるようになりたいのですが、その知識での裏打ちが自分自身ではっきりできないために漠然とした不安感が強くなってしまいます。患者ファーストで患者のことを考えることと、ゆっくりじっくり1人の患者に時間をかけすぎることの乖離は理解できるものの、上手く立ち回れない現状にやるせなさを感じています。
■先生方との貴重な出会い
研修生活の中で2年目の先生や上級医の先生の存在感や信頼感は絶大です。救急外来をはじめ、各科ローテートにおいても先生方に頼りっきりの毎日です。さまざまな科をローテートする中で指導医の先生に感化されることも多くありましたが、特に小児腎臓科の先生は印象に残っています。救急外来に小児患者が多く来ることもあり、小児特有の診察の難しさ、ICの難しさなど様々な知識を教えていただきましたが、中でも検査の意義、事前確率の重要性は毎日のように口酸っぱく強調してくださいました。小児ではひとつひとつの検査の侵襲度が成人に比べて高い傾向にあります。侵襲的なことをする意義を考えて、患者背景から事前確率が低ければ検査の結果に意味が出ないことを徹底的に教えていただき、拙劣ながら考えつつ検査を出す癖が身に付きました。他にも血液内科の先生には救急外来での抗菌薬の杜撰な使用についてご指導いただくなど、本当に情熱を持った先生方に恵まれながら勉強させてもらっています。先生方に教わる耳学問や口訣はいつも診療のなかでかゆいところを的確に解決してくれています。
また、さまざまな診療科を回って先生方に親身にご指導いただくことで、各診療科で重視している考え方や基本となる考え方をなんとなく掴むことができると感じています。将来の選択科に進んだ時だけでなく、今現在でも救急外来において意識しながら診療できることに、各科ローテートの良さを感じています。
■いろんな人に恵まれ
ここまで研修生活を振り返ってみて、本当に充実した研修生活を送っていることに気がつきました。これも診療科の先生方、2年目の先生方、研修の調整をしてくださる教育研修管理課の方々、処方や用法に困った時に相談に乗ってくれる薬剤師の方々、撮影条件や方法の相談、見逃しかけた所見を教えてくれる放射線技師の方々、その他関わっていただいた本当に多くの方に支えられ、助けられているおかげと感謝しています。なかでも一緒に働く同期には本当に恵まれたと感じています。研修医室に行ったらいつでも話を聞いてくれ、不満をぶつけたらどんなことでも受け止めてくれる。一緒に採血の練習をしてくれ、対応に困った症例はとことん話し合って夜遅くまで議論してくれる。心電図に詳しい同期もいれば、読影に強い同期もいて、相談したら一緒に考えてくれる。周りの人たちに救われる場面は数えきれません。こんな人になりたいと思える人ばかりに囲まれ、心から恵まれていると思うと同時に、自分自身も還元できる人間に成長するよう、日々研修に励んでいこうと思う所存です。
最後になりましたが、日頃よりご指導ご鞭撻いただいている先生方、医療スタッフの方々に感謝申し上げ、研修医手記とさせていただきます。
令和7年1月27日
